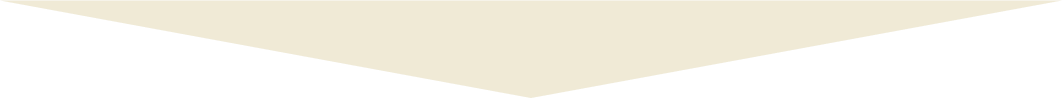人間工学は人間の生理的心理的特性をもとに、人間にとっての使いやすさという観点から、もののあり方を研究し人とマシンの調和を考え、人間に優しい快適設計を行うことを研究目的としています。
日本人にとっては、人間工学の方がなじむかもしれませんが、国際的に通用するのは、エルゴノミクス(ergonomics)です。インターネットでも、エルゴノミクス商品は多数検索できます。「エルゴおんぶひも」までありました。


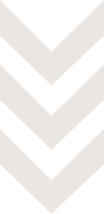
カイロ博物館にはツタンカーメン(紀元前14世紀第18王朝の王)が子供のころに使った椅子があります。これにはフートレスト(足置き台)が用意されていますが、フートレストによって、大きすぎる椅子を子供にアジャストするという考え方です。いまから3千年以上前にそういう考え方があったのです。
イタリア・トリノのエジプト博物館には、比較的保存のよい木製椅子(Kha の椅子) があります。この椅子の背当ては、傾斜していて、着座した人に快適な座り心地を提供しております。
この背当ての傾斜も、座るひとへの配慮です。
16世紀前後になりますが、ミケランジェロの建築のデッサン*の中に、人を描いているばあいがあります。机とイスの相互の関係寸法に注意を払って描かれたものと想像されます。
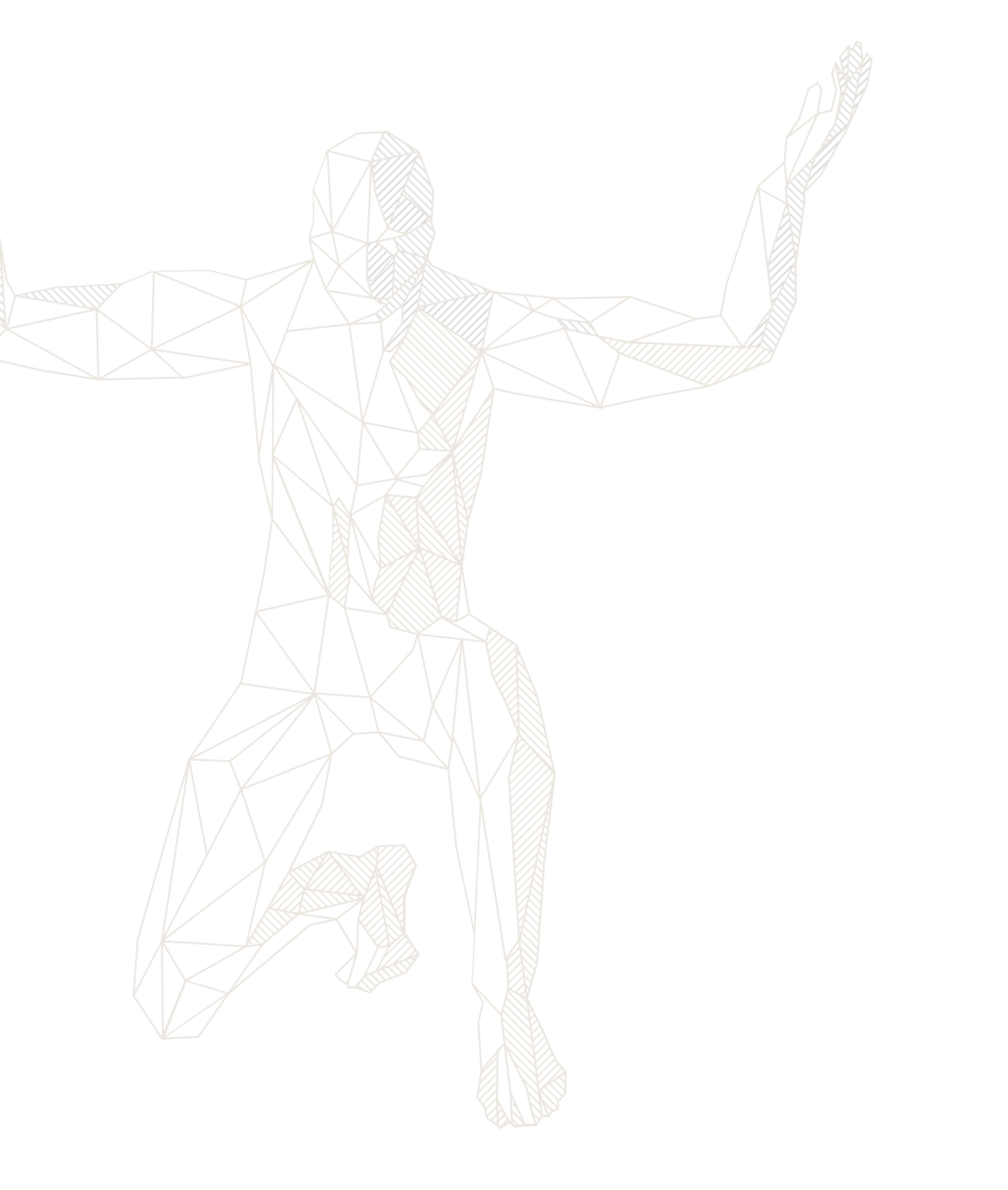
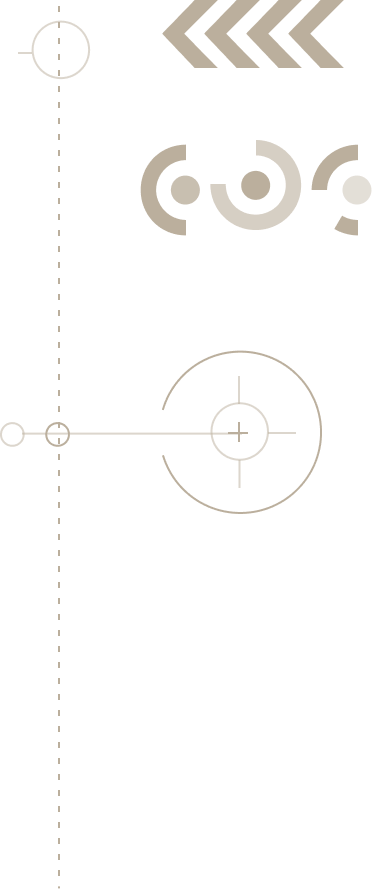
日本も歴史に残る実績があります。13世紀の道元禅師 日本の曹洞宗の開祖 ( 1200ー1253 ) の教え「普勧坐禅儀」には、坐禅を坐法とし、正身端坐としております。道元禅師は、この坐法で座蒲を腰の下に敷くことを提唱しました。 結果として、この座蒲は、その姿勢とあいまって身体の安定性を高めることに寄与しております。また、この座蒲は、それを用いる人の身体形状に合わせてサイズを調整することが現在まで行われているのです。
椅子の座り心地と開発のための医学的なアプローチは、従来以上に人体の医学的な側面を強調したアプローチのことである。その例として、下肢の静脈流と脚のむくみの関係や臀部や大腿部の筋肉の特性を考慮した座り心地のデザインを挙げることができる。
最近では、骨盤や仙骨のサポートが少しずつ話題となってきた。
骨格と病理に関するトピックスが少なくなったものの、椅子と医学の関係は継続している。
たとえば、エコノミークラス症候群に関連して下肢静脈流の測定が最近の例である。